
【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい
2024.02.20
子育て・教育
2021.06.23

この記事を書いた人
牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。
この原稿を書いているとき、東京には4度目の緊急事態宣言が発出され、ゴールデンウィーク明けの5月11日に解除されるはずが、さらに5月末までの延長が決定されました。新型コロナウイルス感染症の新規感染者数も、PCR検査の陽性率も、そして医療現場の逼迫度も、極めて厳しい状況にあります。そして、社会全体の雰囲気にも重苦しいものがあり、それが断続的にすでに1年以上も続いています。
私たちは、この情況に、少し疲れてきてしまっている。そう感じています。昨年のこの時期にあった、いつもとは異なる非日常感、またはちょっとした祝祭感、つまりそれまでとは違う時間が流れ、違う生活を送るという感覚、それはいいかえれば浮き足立っている状態でもあるのですが、そういうものがあったからこそ、みんなでコロナ禍を乗り切りましょう、がんばりましょう、Stay Homeといって、何となく高揚した感じがあったものが、それが1年以上もつづくと、いい加減飽きてきて、気持ちも倦んできてしまう。そういう状態に陥ってはいないでしょうか。

そしてそれが、自粛を呼びかけられても、新型コロナウイルスやその変異株の感染力の強さと致死率の高さ、さらには後遺症の怖さなどが盛んに報道されても、もうなんだかねえ、という諦めというのか、他人事というのか、そういうものとしてしか感じられない、そういう心性を生んでいるように思えます。
そう、飽きてきてしまって、やる気がなくなってしまっている、のではないでしょうか。そして、このような心性が人々の間に広がることは、社会の危機管理としては、とても怖いことです。なぜなら、そういうやる気が起こらない心性は、すぐにもういいやという諦めにつながってしまって、社会全体の緊張感が緩んでしまい、感染症の拡大を防げなくなってしまうからです。
しかも、こういう心性の広がりは、現場つまり医療の最前線で重い負担を抱えながら懸命に踏みとどまって、闘っている人々の心にも影響します。なぜ自分たちだけが、という思いが生まれてしまうと、それももういいや、という気持ちへとつながっていってしまいます。
統計学的な状況の危うさや医療の逼迫に加えて、こういう心の問題をも含めて、いまやわたしたちの社会は正念場を迎えているのだと感じています。これらの意味でも、これまでも社会的な危機管理の鉄則は、短期決戦・迅速な収束であり、はじめに大きく網を被せて、厳しく締めて、状況を落ち着かせたあとで、徐々に緩め、水際対策もしっかりやって、社会全体を安定させることだとされてきたのです。しかし、私たちの政府の対応は、この逆の形となってしまい、ズルズルと事態を引き延ばし、悪化させてきてしまっているといわざるを得ないのではないでしょうか。
私がこの状況を怖いと感じるのは、人々がコロナ禍に対しては、何をやってもダメなのだと諦めてしまうこととともに、政府の対応に対して諦めてしまう、つまり不信感を抱いて、「自衛」することに走ってしまいかねないと受け止めているからです。
それは、政治に対する信頼感が失われ、人々がばらばらに、他の人のことを考えずに、自分だけの行動を取り始める、つまり人々の中から社会が信頼するに足りるものだという感覚が失われてしまい、人々が互いに配慮することを忘れて、孤立していくことにつながっていきます。

そしてそれが、我勝ちに、自分だけは、という感情を生み出し、医療現場の混乱に拍車をかけることになるのではないでしょうか。始まったワクチン接種をめぐる行政対応の混乱ぶりにそれを見ることができるといったら、言い過ぎでしょうか。
それはまるで、「長い箸の寓話」のような状況なのだとはいえないでしょうか。「長い箸の寓話」とは、天国と地獄の話です。
地獄とはどういうところか。そこにはご馳走がたっぷり用意されていて、とても豊かなところなのに、人々は飢えて、互いにいがみあっている。そういう場所です。なぜなら、ご馳走の前には長い箸がおかれていて、その箸を使ってご馳走を食べなければならない決まりがあるのに、その箸は長すぎて、自分の口にご馳走は入らないのです。だから、人々はたくさんのご馳走を前にして、飢えて、争っている。これが地獄です。
これに対して、天国はどうでしょうか。天国にもご馳走がたくさん準備されていて、長い箸がおかれていて、その箸で食べなければならない決まりがある。条件は、地獄と同じなのです。でも、天国では、皆、お腹いっぱいになって、幸せそうに暮らしている。こういう話です。
地獄と天国ではどこが違っているのでしょうか。一点だけなのです、違いは。地獄では、長い箸を使って、自分でご馳走を食べようとして、食べられなくて、お互いにいがみあっているのですが、天国では、その長い箸を使って、お互いに食べさせてあげているから、皆がお腹いっぱいになって、幸せに暮らせている。ただこれだけなのです。
天国は人々が利他的で、地獄では利己的だという言い方もできるかも知れません。しかし、私自身には、それを利他・利己という議論にしたくないという思いがあります。なぜなら、天国の状態が、わたしたちの社会の普通のあり方だと思うからです。
少し考えていただければと思います。もし、皆さんが地獄にいるとして、目の前で子どもがお腹を減らして泣きわめいているときに、それでもお前なんかに食べ物をやるか、といって、何も与えないことなどあるでしょうか。きっと、私のことはいいから、一口お食べなさい、といって、長い箸を使って、子どもの口に入れてやるのではないでしょうか。目の前で、お年寄りが飢えて倒れていて、一口何かを、と求めているのに、勝手にしてろ、といって、何も与えないことはあるでしょうか。やはり、自分のことはよいから、どうぞ一口お食べなさい、といって、その長い箸を使って、食べ物を口の中に入れてやるのではないでしょうか。
そうであれば、そこはもう天国の入り口です。そして、その一口が次の連鎖を生んで、巡りめぐって、自分にも食べ物がやってくるのではないでしょうか。その一口の贈与が、自分への見返りを考えてもいないものであったとしても。
これを純粋贈与といいます。自分への見返りを期待することなく、誰かのために贈り物をすること、そうすることで、結果的に多くの人々に贈与が行き渡り、社会全体が豊かなつながりを持ったものとしてつくられ、それが自分の生活そのものを安定させ、豊かなものにしていく。こういう循環がつくられることになります。

そして、私たちは、自分が生きているこの社会を、このようにして受け継ぎ、つくり、次の世代に受け渡していくことになっているのではないでしょうか。私たちは、私がこの文章を書くときに使っている言葉を、もう顔を見ることもできず、お礼をすることもできない親や先達から受け継ぎ、自分を表現する術を手に入れ、文章を書き、自分の考えを伝えています。
知識も文化も、あらゆるものが、この社会の先輩たちからの贈り物として、私の目の前にあり、私の身体をつくり、意識をつくり、さらに私はこの社会の中に歴史的にも同時代的にも位置づいている、この社会に居場所があると思えるようにしてくれています。これらはすべて、この社会の先達からの純粋贈与です。
これを私たちの社会は、「恩送り」という美しい言葉で表現してきました。この社会を送られた恩を返すのではなく、次の見知らぬ世代へ、見知らぬ誰かへと送っていく、そうすることで、この社会がよりよいものへとつくられていく。こういうことです。
私たちはだから、自分をこの社会に位置づけるためにこそ、様々なことを学ばないではいられませんし、学ぶことで、この社会と自分がつながっていること、自分と誰かとが結びついていることを感じ、それでも自分は自分だという感覚を持つことができているはずです。
そして、だからこそ、この自分を、そして自分が新たに見出し、つくり出した知識や文化を、次の世代に伝えないではいられない。つまり、次の世代に、純粋贈与として、この社会をつなげていかないではいられない存在なのだ、そういうことなのではないでしょうか。
このことにかかわって(これは、第4回の「「みんな」の「気配」」のところでも触れたことですが)、たとえば倫理学・政治哲学者のジョン・ロールズは、私の理解が間違っていなければ、次のようなことをいっています。
ロールズはその著『正義論』(ジョン・ロールズ、川本隆史他訳『正義論』、紀伊國屋書店)で、人々は誰もが、自分や他者の社会的な帰属、生得的な身体の違いや能力、そして資産などがまったくわからず、かつ相互に相手の心理的性向や価値の持ちようなどについても知らない状態となったとき、つまり自分がどうであるのか、自分のアイデンティティがわからない状態に置かれたとき、すなわち「無知のヴェール」に覆われた状態であるとき、社会的に最も不利益を被っていると思われる人々にとって最も有利になるように行動しようとする、といっています。
私はこれを、ロールズによる他者への想像力にもとづく正義の原理であり、「無知のヴェール」の議論の基礎には、ルソーのいうような一般意志への信頼が置かれていて、それは一般意志を発動させるための概念装置だと解釈していました。しかし、昨今の日本社会の状況を見て、この原理が発動するためには、あることが必要なのだと思うようになったのです。
そのあることとは、人々がバラバラに孤立していないこと、つまり他者に対する想像力を持っていること、そういうことではないかと思うのです。
そうでない場合、「無知のヴェール」の状態に置かれることで、それぞれに孤立した人々は、自分が最も不利益を被っている、自己の尊厳が毀損されていると主張して、その状態を改善するように、社会に訴え、自分だけに利益を回すように要求することとなるのではないでしょうか。いまの医療現場やワクチン接種を差配する行政の現場で見られる人々要求のように。
他者との関係すらも切断され、アイデンティティの帰属先をも奪われた「無知のヴェール」に覆われた個人は、他者を思いやる、想像するのではなく、自分こそが割を食っている、被差別者として、その権利主張を何の戸惑いもなく行い、行政や得をしていると自ら見なした他者に要求し、さらには糾弾する。こういうことになってはいないでしょうか。
それはまた、当事者「性」というものではなく、孤立という事態によってつくられた無数の当事者という利己的な存在なのではないでしょうか。しかも、誰もが当事者になれ、自己主張できるのです。
これをシチズンシップの論理ということがあります。本来、シチズンシップはアイデンティティの持つ属性を乗り越え、差別などの社会問題を、自分事とする力を持っています。しかし、その他人事を自分事にするあり方、つまり当事者「性」は、もともと、他者との関係における、他者への想像力に支えられた、慮りによって成立するものとしてあります。
しかし、いまやこの自分事にするということは、そのまま自分だけ、つまり当事者としての「おれさま」を無数に立ち上げることになってはいないでしょうか。そこでは、誰もが皆当事者なのであり、気づいてみたら、本当の当事者の姿が見えなくなってしまっていたという落とし穴はないのでしょうか。

その上、この当事者のあり方は、そのまま一人ひとりが孤立して、その孤立を自己責任だと見なす論理へと容易に転じてしまいます。誰もが他人はおろか、自分のことさえわからない「無知のヴェール」に覆われていて、その「無知」な状態で、自分こそが当事者だと主張せざるを得なくなってしまうのです。
しかも、この当事者である「おれさま」は、自分を当事者だと認めろと他者に主張するのみで、当事者であることの権利保障の請求先を失って、孤立してしまいます。なぜなら、誰もが自分を当事者だと認めろと他者に要求するばかりで、そこにあるのは自己主張のいがみあいだけだからです。
その上、現実には、この自己は権力や権威さらには多数者への依存を招く、つまり長いものに巻かれろという心性を生み出してしまいます。政治が容易にポピュリズムと化してしまい、人々は政治によって癒やされることで、権力との同一化を図り、自分とは異なる人々や、自分の思い通りにならないことで、それを邪魔していると認定した弱い立場の人々を攻撃するようになってしまいます。「正義」を手にするのだといってよいかもしれません。
さらに、この構造は、当事者を個性と読み換えても変わらないのではないでしょうか。誰もが他者に対して自分の個性を認めろと主張しあうことで孤立して、いがみあっているのが、現実の「みんな違ってみんないい」社会なのではないでしょうか。この社会で子どもたちが苦しんでいることは、以前すでに書いたとおりです。
私がこの状態を怖いと思うのは、この「諦め」は学習されるからです。心理学的には、「学習性無気力」と呼んだりします。それは、行動と結果の間に随伴性がないことが重なることで、学ばれてしまう、といわれます。つまり、自分ががんばったのに、結果がともなわず、思っていたような成果が得られないことが繰り返されることで、がんばっても仕方がない、どうせダメに決まっている、と徐々に無気力になってしまい、やることそのものを諦めてしまう、ということです。
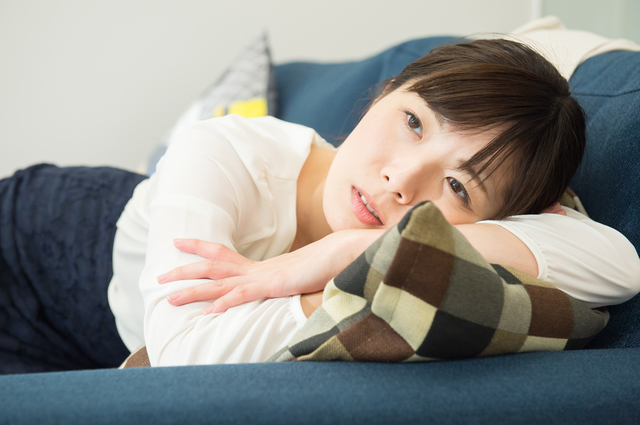
これが社会全体に広がると一つの社会的な心性をつくりあげてしまい、もう、なにをやってもダメだから、とお互いに関心を持ちあうことをやめてしまうようになります。これが、孤立につながりますし、その裏返しで、自分だけは、という利己的な主張につながっていってしまいます。
それがさらに、政治への不信と重なって、人々の間にひろがることで、政府が何をいっても、どうせ意味ないでしょ、という反応になって、人々の行動を制御できなくなりますし、その裏返しで、自分だけは、とサービスの提供を訴えたり、自分こそが「正義」だといっては他者を攻撃したりすることに結びついてしまいます。それがたとえば、ワクチン接種をめぐる我先の行動であったり、行政へのクレームとして公務員攻撃になったり、自粛警察のようにして、他者を取り締まったりするような行動へと連鎖して行き、このことがさらに社会に対する信頼感を低下させてしまいます。
社会の信頼感が薄れ、政治への不信感が募ると、なぜ政府に慰められることを求めてしまうのか。それは、人々が孤立することで、価値判断の基準が揺らぎ、自らの判断で、政治の動きをとらえ、協力的に動くことができなくなり、政府の威を借ることでしか自分を保てなくなってしまうからです。
政治に信頼があるとは、政治を批判的かつ建設的に検討して、自らの立ち位置を決めることができるということですが、それがなくなることで、人々は自らの立ち位置を権威や多数者の中において、自分を安定させようとするようになってしまいます。そこでは、政治そのものがポピュリズムに堕してしまい、理想を語ることができなくなってしまいます。
そうなれば、人々はさらに目先のことに囚われとなって、長い目で社会や自分のことを考えられなくなりますし、さらに他者に気を遣いながら、ともに社会をつくっていこうという気力を持てなくなります。つまり、希望を持って、自分や社会の現状を俯瞰しつつ、理想を持って、変えていこうとする力どころか思いすら失っていってしまうのです。
社会が砂粒化するだけではなくて、「長い箸の寓話」の地獄のようになってしまいます。そこでは、誰もが自分のことしか考えず、誰かを想像しながら、一緒にこの社会をつくり、生活を営むという感覚を失っていってしまうのではないでしょうか。社会は解体し、人々は孤立し、すべては自己責任として処理されて、弱い人が犠牲になってしまいます。
人々が物事を俯瞰的に見ようとしなくなる社会では、人々は同じく物事を深く考えようとしなくなってしまいます。それはまた、なぜ、を問うことをやめてしまい、どのように、が人々の関心事になるということでもあります。

つまり、なぜこのような事態になってしまったのか、とその原因を探り、そこから解決策を探究するということをやめてしまい、どのようにこの事態になったのか、と解釈を求め、どのようにすれば解決するのか、という手続きを問題にするようになるということです。
このことは、社会の心理学化を招きますし、原因を探求するというある意味では不安定な状態を忌避して、手続き上の理由を手っ取り早く手にして、解釈を変えることで、理解したつもりになって安心するというような、価値判断を他人に委ねるような心性を人々に抱かせてしまいます。それはまた、いわばグレーゾーンを嫌い、白黒はっきりさせて欲しいという気持ちと重なりつつ、規範化の厳しい社会、つまり社会の学校化を推し進めてしまうことになります。
社会の心理学化とは、第15回で紹介したように、たとえば生きづらさを抱えた人が、その原因を、幼い頃の母性の欠落に求め、自らの記憶の解釈を変更することで、生きづらさを解消しようとするような、一時期、ハリウッド映画を賑わせたような、人生の単純化つまり人生をわかりやすく、誰でもが思いあたるストーリーへと当てはめて、社会を受け止めようとする人々の心の動きをいいます(たとえば、斎藤環『心理学化する社会』、河出書房新社)。
社会の学校化とは、学校における教育のように、常に正解があり、その正解は一つだと思い込み、さらに単一の基準で人々を評価し、かつそれを学校のきまりのように規範化して、はみ出ることを嫌う、つまりこれも社会を単純化してとらえ、わかりやすいものとしようとする人々の心の動きをいいます(たとえば、上野千鶴子『さよなら、学校化社会』、ちくま文庫)。
単純化、わかりやすさが社会を覆い、人々は曖昧さに耐えられなくなっているかのように見えます。しかも、単純化やわかりやすさは、自分をわからせろ、自分がわかるようにしろ、という誰かに求めるものとしてあって、決して、自分から曖昧さに耐えながら、探究し、価値判断して、自ら解明し、理解し、わかることではないのです。これを消費者的な心性といってもよいでしょう。その場ですぐに手に入れたいのです、わかるということを。
そして、振り返ってみれば、この国の政府が「美しい日本」などといいはじめた頃から、政府や権力に対する批判は、この国や国民に対する否定的な批判として攻撃されることになっていったことに思いあたります。その社会では、格差が広がり、人々の間が分断されて、孤立が深刻化する事態が進行していったのですが、それとともに、先ほど述べたように、シチズンシップの逆説が起こり、政府や権力への批判が、自分に対する批判であるかのような受け止められ方をするようになって、批判者に対する人格的な攻撃や炎上へと向かっていきました。それは今でも続いているのではないでしょうか。
このことは、教育という営みの議論においても起こっていることです。

たとえば、少し前ですが、『日本の教育はダメじゃない』(小松光、ジェルミー・ラプリー『日本の教育はダメじゃない—国際比較データで問いなおす』、ちくま新書)という刺激的なタイトルの本が、面識のない著者から送られてきました。一言でいえば、日本の教育はダメだという「通説」を国際比較の中で問い返して、いえいえ、日本の教育は極めて素晴らしいとまではいえなくても、がんばっていますよ、といおうという本です。
▶小松光、ジェルミー・ラプリー『日本の教育はダメじゃない—国際比較データで問いなおす』(ちくま新書)
なぜ私に送られてきたのか、よくわかりません。私が、このコラム(とはいえないほど、毎回長いのですが・・・・・。すみません)のような社会や教育について愚痴めいた批判を毎回書いているから、反論しようとしたのかも知れません。または著者のお一人は、私がいる職場に以前いらっしゃったようですから、私の同僚たちが皆日本の教育はダメだといっていると受け止めて、そうではないと主張しようと、同僚全員に送ってきたのかも知れません。
内容を読めば、タイトルとは異なって、国際比較を通して、それなりに議論を進めようとする誠実な本であることはよくわかります。
ただ、やはり気になるのは、タイトルにもまして、議論の仕方なのです。日本教育の「通説」を問う、というところから議論が始まるのですが、その「通説」とはいわゆる一般論でしかなくて、本当に通説なのか、ということが問われておらず、さらにそれが通説なのであれば、なぜ通説となったのかが問われていないのです。
強いていえば、「ためにする批判」と私たちが一般にいうような議論の立て方、つまり自分たちの議論が正しいというために、自分たちが解釈した他者の議論を通説だとして立てて、それに対して批判を加える、という議論になっているように見えるのです。そこでは、建設的な批判は、すべて「ダメ」だといっているとして、日本の教育そのものを全否定しているかのような印象を抱かせるようになってしまっています。
また、使われている国際比較データは、それぞれが根拠のあるものですが、間違っている通説だとして批判されている議論で用いられているデータも、それぞれが根拠のあるもので、それに対してそれこそ批判的な検討がなされないまま、自らの論が正しいとして提示されているのです。これでは、相対主義に陥ってしまって、議論ができません。つまり、どっちもどっちであって、せいぜい、お互い干渉しないようにしましょう、という話しかできなくなってしまいます。
批判するのであれば、間違った通説だといわれている説の論拠を正さなければなりませんし、そのためには使われているデータを批判的に検討しなければなりません。それがなされないまま、通説は間違っているといわれても、はい、そうですか、としかいえないままになってしまい、事態の改善に向けての議論ができません。
批判は否定するためのものではなく、反批判によって、現実をよりよい方向に変えるためにあるものです。しかし、この本の議論はそうなってはいないのです。だからでしょうか、結論部分では「もうそういうの、やめませんか」といって、批判的な議論はやめて、現実を見ましょうと提言し、日本の教育は悪くないのだから自信を持ちましょう、という現状肯定の話になってしまいます。
しかも、用意周到に、このようなことをいうと「国家主義的」だといわれるが、そうでしょうか、と予防線まで張っているのですが、それは裏返せば、彼らの議論を批判すると、日本の教育全体を否定することになると言外にいっていることになってしまいます。話が横ずれしていってしまうのです。これでは、よりよい議論ができなくなってしまいます。
単純化の罠にはまってしまい、社会をよりよくする議論を含めた人々の営みは停滞してしまいます。
この議論の単純化やわかりやすさを求める傾向は、実はずいぶん前に哲学者の鶴見俊輔さんがおっしゃっていた「親問題」「子問題」という議論とも通じるものです(鶴見俊輔『大人になるって何?—鶴見俊輔と中学生たち(みんなで考えよう3)』、晶文社)。
▶鶴見俊輔『大人になるって何?—鶴見俊輔と中学生たち(みんなで考えよう3)』(晶文社)
鶴見さんは、こういうのです。「親問題」というのは、自分はなぜ今ここにいるのだろう、という根本的な、自分の存在にかかわるような疑問を抱くことで、答えはひとつではない問題のこと。「子問題」とは、そんなこと考えても仕方がないから、まあ酒でも喰らって、寝てれば、なんとかなる、と考えたり、人生って難しいんだよね、という答えを得ることで、思考をとめたりしてしまうこと、または学校のように答えが一つになるように問いかけを変えて、その答えを得て安心すること、つまり深く「なぜ?」と考えないで、解釈を変えることで、解決したような気持ちになってすませることです。
しかし、鶴見さんは、「親問題」っていうのは、どこまでいっても、ふとしたことで頭をもたげてくるから、そこで切り捨ててはダメだと、子どもたちに語りかけています。
この「親問題」「子問題」をここでの議論に置き換えれば、なぜ?、と問うことこそが大切であって、どのように、と解釈したり理解したりすることは、問題を単純化してしまい、しかも一つの問題で全体を解釈してしまうために、余白がなくなって、異論を差し挟むことができなくなってしまうということでもあります。
そして、この議論で私が大学の教員として気になるのは、第15回の議論でも紹介したように、意見をいうと相手の人格を批判するかのように受け止められて、人格をかけた反撃が始まるという学生たちのとらえ方ともかかわって、ここ数年、卒論や修論の議論が、「子問題」から入るようなものばかりになってきているということなのです。
たとえば、こんなことです。ある学生が卒論の構想を持ってきたとします。そこにはまずタイトルがありません。いきなり「リサーチクエスチョン1」として「子どもの学力格差がなぜ生まれているのかを問う」と書かれています。それを受けて、この問題を問うために、「リサーチクエスチョン2」として、「子どもの学力と家計の経済格差の関係を調べる」「子どもの学力と日常生活習慣との関係を調べる」とされ、さらに「リサーチクエスチョン3」として、「そのためにアンケート調査を行う」「アンケート調査から抽出して、数名の子どもにインタビューを行う」と書かれています。
調査対象者の個人情報の保護その他の問題があることは、ここではおいておきます。ここで、私からは「なぜ、君はこの問題を扱いたいと思うの?」という質問をします。なぜなら、このきれいにまとめられているリサーチクエスチョンは、1から3まで何をやるのか、どうやるのか、が書かれているだけであって、なぜ、子どもの学力格差を扱わなければならないのか、が書かれていないからです。つまり、なぜ(why)、ではなくて、どうやって(how)、が書かれているだけなのです。
この問いに対して、このところ多くなっているのが、「いけませんか」という反問です。「いけませんか」というのは、自分がやりたいといっているのに、先生はやるなというのですか、という問いかけなのです。
そこで、私は「いや、そういうことではなくて、君がなぜこの問題に関心をもって、それを卒論で扱いたいと思ったのか、動機は何なのか、と聞いている」と問い返すと、「やりたいからです」という返事になってしまい、議論が深まらないのです。
「なぜ?」を問うことは、なぜ自分はそれを問題だと思うのか、と自分を主語にして問い返しをすることにつながります。それは、その問題を自分事にして、自分をその問題の当事者にしていくことにつながっています。
ですから、たとえば上記の課題設定であれば、次のように問いを突き詰めることが求められます。
子どもの学力格差が生まれているのは問題だ。なぜなら学力格差が人生の格差につながるからだ。
なぜ自分はそれを問題だと思うのか。なぜなら学力が低いことで差別される子どもがいてはいけないと思うからだ。なぜなら学力そのものが本人の力ではどうにもならないものの影響で決められているとするならば、この社会は子どもの学びの出発点においてすでに不平等だからだ。
さらに、学力が子どもの人生を決めてしまうような制度の設計に対しても疑問がある。なぜなら人の能力は学力という一面ではとらえられないからだ。
と、どこまでも問いを深めていくことで、その学生自身が自分のことをどんどん深めていくことにつながり、そこから改めて論文の構想を描くことで、なぜ格差が生まれているのかが分かれば、それをどうしたらよいのかが導かれて、次の実践につなぐことができるからです。
「親問題」とは、その問題を自分事としてとらえようとする想像力を働かせることだ、といってもよいでしょう。

私が大学の教員としてこのことを残念に思うのは、この学生のような研究や学習への向きあい方つまり態度ですと、それが本人の人生やこの社会に生きているということと関係がないもの、つまりなんのために学び、研究しているのかがわからなくなってしまうからです。
このことを少し広げれば、自分の日常生活と社会の様々な問題とが関係のないものとなってしまうということです。だから、人々は自分が生きている意味に飢えてしまい、意味に苛まれるようになってしまうのではないでしょうか。自分が生きていることと学びや活動が関係がない、つまり社会に自分がいることが他人事になってしまうということです。
しかもこの議論は、たとえば吉野源三郎さんの『君たちはどう生きるか』(吉野源三郎『君たちはどう生きるか』、岩波文庫)で語られる話とつながります。
おじさんが主人公のコペル君に語る話に、たとえばこんなものがあります。「ニュートンの林檎と粉ミルク」という話です。概括すると味がなくなってしまうのですが、こういう内容です。
ニュートンが林檎の木から林檎の実が落ちるのを見て万有引力の法則を発見した、という故事から、ニュートンはこう考えたのではないかと、おじさんの大学時代の友だちがいった。林檎は3、4メートルの高さから落ちたが、それが10メートルだったらどうか、15メートルだったら、100メートルだったら、もっと高くしていって、何千メートル、何万メートルと伸ばしていって、とうとう月の高さまでいったと考える。すると重力が働いている以上、林檎は落ちてくるはずだ。でも、月は落ちてこない。なぜなら、月の遠心力とお互いの引力とが釣り合っているからだ。しかしそれはニュートン以前にすでにケプラーらが明らかにしていた。ニュートンの発見とは何かというと、地球上の物体に働く重力と天体の間に働く引力とを結びつけて、その二つが同じものだということを実証したところにある。

それで問題は、この二つの力がどうしてニュートンの頭の中で結びついたのか、ということだ、と。それは、ニュートンが林檎を木から落ちたと、当たり前のようにとらえるのではなくて、それをどんどん地球から離していって、最後には天体間の引力にまで行き着いた。その想像力こそが尊いのだというのです。
ここで、おじさんはこういうのです。「あたりまえのことというのが曲者なんだよ。わかり切ったことのように考え、それで通っていることを、どこまでも追っかけて考えてゆくと、もうわかり切ったことだなんて、言っていられないようなことにぶつかるんだね。」(同上書、81-82頁)
上記の私の問いかけと同じなのです。わかり切ったことや「子問題」をなぜ、なぜ?、と突き詰めていくと、もうわかり切ったことなどといってはいられないような大きな問題、つまり「親問題」に行き当たるのです。
そして、この話から、コペル君は、この社会の人のつながりへと想像を広げていきます。粉ミルクが自分の手元にあって、自分が毎日飲むことができるのは、オーストラリアに牛がいて、その乳を搾る人がいて、原料を作る人がいて、それを加工する人がいて、それを輸送する人がいて、それを売る人がいて・・・・・・、とこの社会が自分の見知らぬ人の労働とつながりで成り立っているからこそ、自分は粉ミルクを手にすることができているということに思いあたるのです。
コペル君はこの想像をさらに広げて、このつながりが、粉ミルクだけではなくて、この社会のあらゆることに適用できることを発見していきます。そしてこういうのです。「僕は、これを「人間分子の関係、網目の法則」ということにしました。」(同上書、88頁)
これに対しておじさんはさらに、コペル君に「人間分子の関係」というのは「生産関係」と呼ばれるもので、それは、生活に必要なものの生産から人間が相互に依存している網目の構造を表しているということを伝えます。コペル君は、おじさんの話に触発されて、想像力を広げることで、いわば社会科学的なものの見方を身につけていたのです。
これは繰り返しますが、鶴見さんのいう「子問題」から「親問題」をとらえること、そうすることで、この社会の様々なことを自分事としてとらえ、自分が生きることと社会のあり方とがつながっていくことを意味しています。
社会科学的なものの見方とは、何も対象を突き放して客観視することだけではなくて、対象を俯瞰しながら、自分事のようにしてとらえ、社会で自分が生きることとこの社会のあり方を重ねる想像力を働かせることでもあるのです。そしてそれが、私たちを探究へと誘っていくことになります。
そしてそこでは、河野哲也さんがいうように、「「研究すること」と「生きていくこと」が分けられない社会」がつくられていくようになります(河野哲也『問う方法・考える方法—「探究型の学習」のために』、ちくまプリマー新書、12頁)。そこでは飽くまで、社会が自分事になっていることが大切なのですし、そのためには見知らぬ人々への想像力を羽ばたかせること、他者をおもんぱかる力が重要なのです。
▶河野哲也『問う方法・考える方法—「探究型の学習」のために』(ちくまプリマー新書)
私が危惧するのは、社会が「諦め」を学んでしまうことで、子どもたちがこの想像力を培うことができず、結果的に自分の人生を諦めてしまうことになるのではないか、ということなのです。

コロナ禍での、このところのおとなの行動と政府の対応は、子どもたちの人生に大きな影響を持っていることを、私たちは改めて受け止めなければならないのではないでしょうか。
\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/
\ 最新情報が届きます! /
牧野先生の記事を、もっと読む
連載:子どもの未来のコンパス
#1 Withコロナがもたらす新しい自由
#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由
#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤
#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」
#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶
#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校
#7 Withコロナが暴く学校の慣性力
#8 Withコロナが問う慣性力の構造
#9 Withコロナが暴く社会の底抜け
#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為
#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢
#12 Withコロナが予感させる不穏な未来
#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係
#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ
#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?
#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み
#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ
#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体
#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ
#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの
#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ
#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗
#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1
#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5
#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2
連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ
#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る
#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく
#3 子どもの教育をめぐる動き
#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”
#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと
#6 「学び」を通して主役になる
新着コンテンツ