
【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい
2024.02.20
子育て・教育
2021.09.24

この記事を書いた人
牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。
この連載も今回で第20回となります。連載第1回の記事の掲載が2020年5月でした。
連載開始時には、10回くらいでコロナ禍から抜けだし、次の社会の学びについて議論できるのではないかと考えていました。しかし、そうは問屋が卸してくれませんでした。
しかも、事態は悪化するばかりです。この原稿を書いている今日、政府は4回目になる緊急事態宣言発出対象の自治体を拡大し、全国で21都道府県が緊急事態宣言下に入ることになりました。首都圏や関西圏だけでなく、お盆休みによって各地に広がったと思われる感染が、感染者数の急増となって、各地の医療を襲いつつあります。
東京都を含めた首都圏の医療はすでに崩壊状態で、連日、救急搬送される感染者が受入先がないままに自宅に戻されたり、また自宅療養中の患者が容態が急変して亡くなったりする事例が相次いでいます。
ワクチン接種が進んでいるとはいえ、高齢者から順次進めていった接種は、いまだに若者世代にまで回っておらず、夏休み明けの学校で、子どもたちの感染者クラスターが発生することが危惧されています。いくつかの自治体では、夏休みを延長し、子どもたちの学習のために教材を教師が自宅に届けたり、オンラインでの授業を実施したりすることにしたと報道されています。
そして、このような感染の急拡大期に、オリンピックとパラリンピックの開催です。もともとは、東日本大震災からの復興を世界にアピールするとされていたオリパラは、開催が決定した後に不祥事続きで(さらに、招致過程についても贈賄などの不正があったのではないかとの疑惑が持ち上がっています)、その後、コロナ禍の世界的な拡大で1年間延期され、いつの間にかコロナに打ち勝った証の大会だといわれはじめ、それも難しくなると、なんと首相の個人的な1964年東京大会の思い出を持ち出して、思い出づくりの大会だという、何とも理解できない理由での開催となりました。それだからでしょうか、オリンピックは開会直前まで問題だらけで、とくに企画側の人材の劣化(人のあり方としてどうかと思うようなこと)が目立つものとなってしまいました。

それをカバーしてくれたのが、ボランティアを担った市井の人々で、各国のアスリートからそのホスピタリティが賞賛されました。ここに私たちは、この社会の確かさを感じることができます。この社会を担っているのはこういう人たちなのだ、と。
オリンピックの開催についても、東京都教育委員会は学校観戦を最後まで主張し続け、子どもを東京都の学校にやっている知人たちは、皆不安を訴えていました。そこでいわれたのが、子どもたちの思い出づくりと教育的意義、ということでした。
私が聞いた話では、学校単位で観戦する種目が決まっていて、その会場までは公共交通機関を使って移動することが都から示されていたとのことです。そして、学校単位で観戦するので、学校行事として行い、不参加の子どもは欠席扱いとするとまでいわれたとのことです。
先生方も困惑されたのではないでしょうか。私の知人の保護者たちは、思い出づくりのために子どもの健康を犠牲にするのか、と憤っていましたし、さらに出欠を持ち出して、強制しようとする都の方針にも怒りを隠しませんでした。
しかも、学校現場では、子どもを観戦させたい保護者と、子どもの健康を第一に考えて、リモートで応援すればよいとする保護者との間で意見が分かれ、教師が板挟みになって苦しんだという話は、枚挙にいとまがありません。その上、先生方も都の職員だからでしょうか、学校で判断することができずに、保護者の意向を聞くという姿勢に終始したといいます。

ここに子どもが巻き込まれているとすると、とても教育的ではない状況が学校に生まれていたことになりますし、子どもの間を観戦支持派と反対派に分断することになってしまったのではないでしょうか。
結果的には、保護者が動いて、ほとんどの学校が観戦を取りやめるということで、なんとか事態を収拾したようでした。知人の保護者たちは「健康や命よりも思い出づくりのほうが大事なのか?! 何が教育なのか!」と憤っていましたが、その気持ちはよくわかります。
確かに一生に一度のオリンピックなのかも知れません。そしてアスリートの努力と鍛錬の結晶である活躍を生で見ること、大会を成功させるために多くの人々が献身的にかかわっている現場を体験すること、こうしたことの教育的な意義を否定するものではありません。
しかし、それは、子どもたちの健康や命を危険に晒してまでなされるべきことなのだろうか、という疑問も素朴にわいてきます。極論をいえば、健康や命と教育的意義のどちらが大切なのか、という二つを天秤にかけることを超えて、教育とは一体何なのかという学校が存在していることの根本的な意味を問うことにつながるのではないかと思うのです。
そして、パラリンピックです。コロナ禍拡大の状況は、オリンピックの時の比ではありません。東京でも連日、新規感染者が4000名、5000名を超え、PCR検査の陽性率は2割を超える日々が続いています。神奈川や千葉・埼玉でも新規感染者数は過去最高を記録し続けている状況です。
こんな中で、東京都教育委員会は、教育委員5名のうち4名が学校観戦に反対だとの意見を提出しても、子どもたちの学校観戦を、感染防止策をとった上で行う、との方針を変えないまま、パラリンピックが始まっています。もし、学校観戦が全面的に実施されれば、都内14万人の子どもたちが観戦することになるとのことです。
そしてその実施の論理が、教育的意義なのです。この措置に対して、私の知り合いの保護者たちは、もう、呆れてものがいえない、といっています。自分の子どもだけになっても、欠席扱いだといわれても、保護者の判断で行かせないし、子どもだって不安に思っていて、行きたくないといっている。ここで、保護者が折れて、教育委員会の方針に従ってしまっては、結局、子どもたちにおとなは事なかれ主義だ、長いものに巻かれていればいいのだ、しかも自分の親までもがそうなのだという、おとなの醜い世界を見せてしまうことになる。
そもそも、遠足も運動会も中止になったのに、なぜ、オリパラは学校単位で半強制的に行かなければならないのか。子どもになんと説明するのか。首相が思い出は大事だといっていて、それが教育的意義を持っているとされているからなのか。
それなら、遠足や運動会は、簡単にやめてもいいくらい、いい加減な教育的意義しか持っていないのか。ならば、学校でそれを行事として行うのは、学校の教育的意義も軽いものだということなのか。わけがわからない。
教育的意義というのは方便、もっといえば嘘で、本当はカネとか、メンツとか、利権とか、ドロドロした論理が働いているに違いない。そんなものに教育的意義など認めたくない。だから、もう、行政や学校が何をいおうとも、自分の子どもだけは自分が守る。こうきっぱりという知人は少なくありません。

私もそう思います。教育的意義とはなんなのでしょうか。それは、おとなの都合に子どもを巻き込むための常套句なのではないでしょうか。
繰り返しますが、アスリートたちのたゆまぬ努力や鍛錬の結晶である競技や、お互いに尊敬しあい、尊重しあう態度、大会運営にかかわる関係者の思いと行動、こうしたものが編み上げる感動の空間、こういう場に身を置くことの意義には大きなものがあると、私も思います。
そして、これがいわゆる平時の、オリパラの開催を素直に喜び、祝福できるような状況下であれば、子どもたちが学校単位で観戦することも、学校教育の延長上で意味のあることだといえると思います。
しかし、招致の初めから不祥事続きで、しかも世界的なコロナ禍の拡大で延期となり、さらに状況が悪化している中で、その上、通常の学校行事が行えない状況下で、それでも子どもたちを学校単位で観戦させることに教育的意義があるという、いえ、むしろ強弁する教育行政の責任者の論理は私の理解を超えています。
本当に教育的意義を考えるのであれば、子どもたちには、まず、君たちをおとなの事情に巻き込んでしまって申し訳ない、と率直に謝罪することではないでしょうか。
その上で、君たちも社会の大切な一員なのだから、命の危険を冒してまで、観戦することはない。家で、家族や友人・知人と一緒に、リモートでアスリートを応援して、感動をオンラインでみんなと分かちあって欲しい。しかも、君たちにもコロナ禍の拡大を防ぐ重要な役割がある。オンラインでも誰ひとりとして取り残さないように配慮しあい、お互いを尊重しあって、助けあい、コロナ禍を一刻も早く終熄させるために、力を貸して欲しい。君たちもこの社会の重要な一員だし、担い手なのだから。と、彼らの存在をきちんと社会に位置づけること、そして自分が置かれた条件の中で、何ができるのかを、自分の頭で考えてもらい、ひとりで悩むのではなくて、仲間と一緒になって解決策を模索するよう促すこと、こういうことなのではないでしょうか。

このままでは、本当に、子どもたちがおとなに対する信頼を失い、それが社会に対する信頼の喪失につながってしまうように思えて心配でなりません。それこそ、教育的意義など微塵もないといわざるを得ないのではないでしょうか。この社会の制度としての教育は、この社会の次の担い手を育て、社会の持続可能性を高めるためにこそあるのですから。
いまの状態は、次の担い手である子どもたちの社会に対する不信感を高め、それがこの社会の持続可能性を毀損するだけでなく、子どもたち自身に、この社会には自分の居場所がなく、自分は大切にされていないという感覚を持たせることになってしまうのではないでしょうか。
作家で演出家の鴻上尚史さんは、元麹町中学校長・工藤勇一さんとの対談で、「先生を信頼したかった」、でも、自分にとって学校はそういう場所ではなかったといっています(工藤勇一・鴻上尚史『学校ってなんだ!—日本の教育はなぜ息苦しいのか』、講談社現代新書)。
▶工藤勇一・鴻上尚史『学校ってなんだ!—日本の教育はなぜ息苦しいのか』(講談社現代新書)
工藤さんはそれを受けて、学校の「改善」(工藤さんは、学校改革というと大上段に構えてしまって、抵抗が大きくなるが、改善ならいくらでもできるといいます)は、現行の制度の中で十分可能で、先生たちの意識を一つにまとめることでそれはできる。その時の根本的な問題は、対立軸をなくす課題を設定すること、それは「僕は生徒の命だと思うんだよね」という校長のことばだといいます(同前書、41頁)。
そして子どもには、「自分たちの住んでいる社会そのものを、責任もって変えてごらん」と問いかけるのだと、指摘します(同前書、39頁)。それが、かの有名な麹町中学校の改革(改善)につながったのだといいます。
この二人はどちらもが、学校で生徒も先生も、社会の当事者となることを説いているといえます。鴻上さんは、「先生を信じる」ことで、そして工藤さんは「生徒を信じる」ことで。
しかし、麹町中学校の改革が社会の耳目を集めたように、つまりそれがいまの学校では極めて困難で稀なケースとして受け止められたように、そして鴻上さんが「先生を信じたかった」のに、できなかった、と述べているように、子どもとおとなが共に信じることで社会の当事者となることができないような学校であるのであれば、それはなぜなのかを問わなければなりません。
誰も共に信じることができず、社会の当事者になれない学校、このことを深く問い返しているのが、奇しくも8月に新たな進展があった「旭川いじめ事件」なのではないでしょうか。
すでにマスコミなどで詳報されていますから、詳しくは述べませんが、私個人は、この事件の加害の状況は、いじめを超えて犯罪だと思いますし、嫌なことをされ、させられたという以上に、人間としての尊厳を否定され、生きる希望を失った被害者の子どもの辛さと保護者の無念を思うと、胸が痛くなる感覚を覚えます。そしてその感覚は、私を過去のある記憶へと追い立てます。
ある自治体で、いじめ自殺があり、その検証作業を終えた第三者委員会から報告を受け、今後の施策を検討するための市民シンポジウムが開かれ、その場に、指定討論者として参加することとなったのでした。
自ら命を絶たなければならないほど追いつめられた被害生徒のことを思い、また加害生徒そのものが学校に疎外感を感じていた、そのことの辛さを思うとき、いじめは起こるべくして起こってしまうものだという思いとともに、子どもたち一人ひとりのおかれた状況の過酷さに、胸が押し潰されるような苦しさを感じたのを覚えています。

第三者委員会の検証では、学校という現場で、いじめがエスカレートしていく様が明らかにされ、シンポジウムではそれをもとに、今後の施策のあり方についての提言がなされました。そして会場の市民からも、この事件を他人事とせずに、自分事として受け止め、学校と地域との連携を強めることの必要性が訴えられ、さらに、学校のリスクマネジメントを強めることや教職員の感度を高めること、そして教職員が子どもに向きあえないような勤務となっていたのであれば、それを改めるように負担軽減すること、などが提言されました。
会場では、子どもたち自身が、人権教育や市民性教育の重要性を語り、見て見ぬふりをしない勇気を持つことを誓いあいました。誰もが、自分を当事者と位置づけ、いじめ再発の防止を訴えあう、ある種の感動的な空間が出現することとなったのです。
しかし、私にはどうしても拭えない違和感が残ったことも事実です。
皆さんがいっていることは確かにそうだと思うのです。
誰もがいじめの当事者であり、いじめをなくすことに努めなければならない。そのためには誰もが、いじめを自分事として受け止め、その行為そのものが起こらないような関係をつくりだすことが重要だ。
学校には、子どもたちと正面から向き合うことのできる教職員がいて、一人ひとりの個性を尊重しあう関係をつくり、保護者も地域社会の人々も、子どもたちを認め、受け入れ、彼らの居場所をつくらなければならない。

このことは、その通りだと思います。しかしそれでも、どうしても違和感が残る気持ちを抑えることができませんでした。
誰もが子どもの教育の当事者だからこそ、保護者は自分の子どものことに懸命になり、学校にクレームをつけ、教師は子どものことを思うからこそ、仕事が増え、多忙になり、それでも自己犠牲的に働こうとするのではないのでしょうか。地域社会の人々も、子どもを大切に思うがために、学校に意見をいい、行政に苦情をいうのではないのでしょうか。そして、何よりも子ども自身が当事者でないことはあり得ません。
しかし、この当事者のあり方つまり当事者性は、それぞれがそれぞれの方向を向いていて、子どもの当事者性と重なってはいないように見えるのです。子どものことを思いながら、子どものためといいながら、それぞれの立場からの当事者性が、学校という場に収斂して、立ち現れている。そう見えるのです。
ところが、そうではないようにも思います。このバラバラに見える当事者性は、子どもが抱いている当事者性と重なっているのだ、と。
どういうことなのか、考えてみます。たとえば、学校をすべての子どもたちにとって居心地のよい場所にしようと、誰もがいいます。そして、個性を認めあおう、「みんな違ってみんないい」といわれもします。しかし、この「みんな違ってみんないい」には、棘が潜んでいるのではないでしょうか。「いい」とは、どういうことなのでしょうか。「いい」とは、誰にとって「いい」のでしょうか。「いい」とは誰が判断するのでしょうか。
また、世界で一つだけの花をそれぞれが咲かせることがよいことだ。みんながそれぞれの個性を持っているのだから、尊重しあおう、といいます。しかしそこには、世界で一つだけの花を咲かせることで、認めあおう、尊重しあおうということ以上の何かがそっと滑り込んでいるのではないでしょうか。
それぞれが自分の花を咲かせることは大事だ。誰にとって? 「大事」とはどういうことなのか。咲かせられない人は、「大事」ではないのか。咲かせられないことも個性なのか。ならば、個性とは何なのか。お互いに認めあおうということで、大事な個性とそうではない個性を分けてしまうのではないか。
きれいな花にも、他の花に引き立てられて真ん中に立つ花と、それを引き立てる脇役の花とがあるのではないか。そもそも尊重しよう、認めようという時の基準は何なのか。どうであれば、認めあったことになるのか。こういう疑問が次から次へと湧いてくるのです。

個性を認めること、大事にすることが、この社会では無意識に、そのまま「評価」につながっているのではないでしょうか。しかもそれは、ひとりの人格を評価することになっているのではないでしょうか。
なぜなら、個性はそのままその人の人格そのものをつくっているものだからです。そうだとすれば、一人ひとりの個性を認めあおうといった途端に、それはその人の個性を評価しよう、人格を評価しようということになってしまっているといえるのではないでしょうか。
だからこそ、人は自分の個性について少しでも否定的に触れられると、攻撃的になってしまうのだとはいえないでしょうか。誰もが、自分の人格のあらゆる面を他者から評価されているという感覚になってしまっているように見えます。
人々は、自分というものそのものの核を持たず、つねに評価に晒され続けることで、自分を守るために他者に対して攻撃的になり、その裏で、行政や権威に依存して、自分のことを尊重せよ、評価せよと要求する。こういうことになってはいないでしょうか。
子どもたちを認めよう、一人ひとりを大切にしようとするがために、おとなたちはそれぞれの立場から、バラバラな当事者性を主張することになっていますが、それは、子どもたちが学校を含めてこの社会の中で、それこそ逃げ道がないかのように、評価に晒されていることのそれぞれの側面を切り取ったものでしかないのではないでしょうか。
こういう社会で、子どもたちを本当に救うことができるのでしょうか。
こうした子どもたちの事態に対して、たとえば第三者であるいわゆる有識者たちは、死を選ばなければならないほどにつらいのならば、学校から逃げろ、といいます。またオルタナティブの道があるのだから、学校にこだわり続けることはやめろ、ともいいます。
行政的にも、経産省が進めている「未来の教室」事業は、子ども一人に一台ICT端末を持たせて、学習の個別化を徹底し、いわば個別最適を全体最適へと結びつけることで、学校に代わるオルタナティブの学習機会を提供しようとしています。そして、いわゆる「教育機会確保法」に示されるように、学校以外にも学歴を認定する仕組みができつつあります。
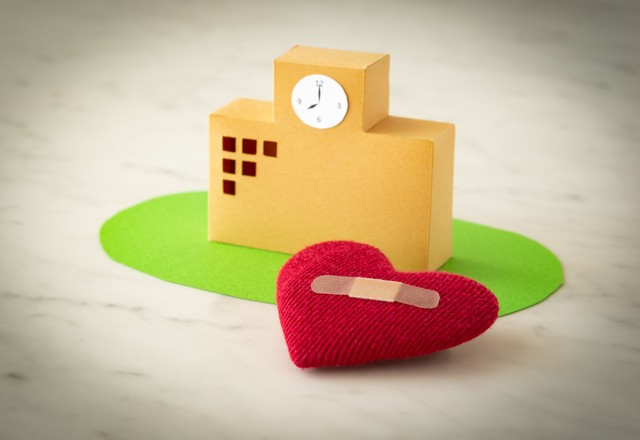
しかし、子どもたちは学校から逃げることなく、命を絶ってしまうのです。
それは、SNS自殺でも同じことではないでしょうか。LINE外しで死を考える子どもたちがいます。そんなに苦しいのであれば、LINEから自ら脱ければよいではないか、とおとなたちは考えます。しかし、子どもたちはLINEから脱けることができずに、死を選んでしまうのです。なぜなのでしょうか。
私は、ある自治体の不登校問題対策協議会の座長を担当してきました。この自治体では、もう30年以上も学校の教師が苦しい実践を継続し、不登校をなくそうと努力しています。しかし、結果はいたちごっこであり、悪化する一方だといわざるを得ません。子どもたちを学校に戻そうとする力が働いていて、子どもたちの現実との間にズレがあることは確かなのですが、それ以前に、学校から降りて、他の道を選ぶという選択肢が機能しないのです。
この自治体では、不登校になってしまった子どもたちのためのフリースクールが十分に用意されています。そして、幾人かの子どもたちはそれを利用しています。しかし多くの子どもたちは、学校に留まったまま、不登校を繰り返し、心を病んでしまうのです。オルタナティブな教育機会に進んだ子たちも、今度はそこからこぼれ落ちてしまうのです。学校に囚われになったまま。
なぜ子どもたちは学校から逃れられないのでしょうか。学校にはここまで子どもをとらえて放さない魔力があるのでしょうか。子どもたちには逃げる先の「社会」はあるのでしょうか。
このことを考えないで、学校から逃げろ、オルタナティブがある、そして子どもの個性を認めよう、お互いに受け入れあおうと主張してみても、無意味なのではないでしょうか。
視点を変えてみましょう。学校が問題なのではありません。子どもをとりまく、そして学校をとりまく社会が問題なのではないでしょうか。
学校が子どもをとらえて放さない、または子どもたちが学校に囚われになっている、のではなくて、子どもたちは学校から出ていく場所がなく、その術がないのではないでしょうか。家庭にさえも。
残っているのは、自分の部屋というちいさな世界か、精神の小箱か、死を選ぶことだけ、つまり自分の中に閉じこもることだけなのではないでしょうか。つまり、子どもたちには「社会」など存在していないのではないでしょうか。
子どもたちには社会など存在してはいない、ましてや地域など、と課題をおいたとき、見えてくるものは何なのか、このことが問われなければなりません。
子どもたちには安心して自分を預けることのできる社会など存在してはいないのではないでしょうか。常に評価に晒され、他人との比較の中におかれ、序列化されてしまう、そういう圧力構造をこの社会は持っていて、それが野放しになったまま、子どもたちが苦しむ事になっているのではないでしょうか。
そこでは、オリパラの感動までもが、序列化されてしまうように受け止められます。その磁場では、アスリートたちの努力の結晶である競技の成果が、感動の度合いとして評価され、感動を与えられないアスリートはいくら努力していても、いくら苦しい鍛錬に耐えていても、評価されないこととなってはしまわないでしょうか。
しかも、このコロナ禍の下で、暗い雰囲気を吹き飛ばそうとするからなのか、また日本人選手のメダルラッシュだからなのか、マスコミの報道も、いつもにまして、ヒートアップし、感動を強調しようとしているかのように見えます。
障害児を持つ親である知人が、この風潮に不安を感じるといいます。パラリンピックのテーマが、「多様性と調和」であることはとてもよいし、障害者でも努力によって、こんなにも素晴らしい競技や演技ができ、人を感動させることができる、そのことはとても素晴らしいことだと思う。でも、それが過度に強調されることで、そうできない障害者はダメな障害者だ、と評価されることにはならないだろうか、というのです。
また、障害児の存在について、健常者の社会から見たら、存在の意味がないような子どもであっても、どんな子でもその家族にとってはかけがえのない存在なのだ、といういい方についても、この私の知人は同様の感じを受けて、不安だといいます。かけがえのない存在という価値づけがなされなければならないのだろうか、というのです。かけがえのなさを価値づけされない、ただそこにいるだけの障害者は意味がないのだ、と評価され、序列化されて、障害者の中でもランクづけがなされてしまうのではないか、と心配になるのだというのです。

それは結果的には、あらゆることを、感動までをも評価して、序列化し、序列の低い人は生きている価値がないという判断を下すことと等しいことになるのではないか。それが不安で仕方がない、というのです。
いろいろなことができなくても、人の役に立たなくても、家族を癒やすということすらできず、ただそこにいるだけの障害者でも、いえ、障害者ではなくても、すべての人が、ただそこにいるだけで、受け入れられ、認められる、なんの評価も序列化もなしに、という人の存在のあり方は、この社会では求めても求められないものなのでしょうか。私たちは、常に誰かを価値づけ、また誰かに価値づけられなければ、いられない存在なのでしょうか。
コロナ禍の下で強行されたオリパラが、感動を宣揚されることで、評価と序列化に結びつき、結果的に差別を助長したり、新たな差別を生んだりするようなことになるようでしたら、思い出づくりどころか、教育的な意義はあるのでしょうか。私たちは、こうしたことをこそ、子どもたちに伝えなければならないのではないでしょうか。
評価に晒され、序列化され、差別され続けた子どもたちは、他人をそして社会を信頼する力を奪われてしまいます。「人を信頼すること」がいかに子どもたちの自立にとって重要であるのかは、長期にわたる指導困難高校への取材を通して、ノンフィクションライターの黒川祥子さんが語っているとおりです(黒川祥子『県立!再チャレンジ高校—生徒が人生をやり直せる学校』、講談社現代新書)。
▶黒川祥子『県立!再チャレンジ高校—生徒が人生をやり直せる学校』(講談社現代新書)
私たちがやらなければならないのは、感動を美化して、価値化することではなくて、それを社会と人そのものへの信頼へと醸成することなのではないでしょうか。
そこでは、私たち自身がこの社会の中で身につけてきてしまった評価と序列化の無意識の感覚を意識化して、unlearn(学びほぐし)しなければならないのだと思います。
子どもたちへの教育的意義をいうのであれば、アスリートの努力の結晶に感動し、人間の素晴らしさ、可能性を改めて感じとり、パラアスリートの活躍を目にして、知らず知らずのうちに身につけていた障害者への固定観念を脱ぎすてることを超えて、私たち自身が社会の中で互いに価値づけあい、序列化しあうことで、互いに信頼することを忘れてしまっている現実、感動すらをも価値化し、序列化してしまおうとする私たちの無意識の意識、こういうものに気づき、その固い観念をほぐして、共に受け入れあい、信頼しあえる社会をつくることに意識を向け、行動すること、それを子どもと語りあい、また実際に行動に移すこと、こういうことが大切なのではないでしょうか。
その場には、おとなが子どもを信頼し、子どもがおとなを信用する関係ができているのではないでしょうか。それこそが、子どもたちの社会への信頼を醸成することになり、彼らが社会の担い手として、自ら立とうとすることを支えることにつながるのだと思います。

このことが、オリパラによって私たちに突きつけられているのです。
\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/
\ 最新情報が届きます! /
牧野先生の記事を、もっと読む
連載:子どもの未来のコンパス
#1 Withコロナがもたらす新しい自由
#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由
#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤
#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」
#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶
#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校
#7 Withコロナが暴く学校の慣性力
#8 Withコロナが問う慣性力の構造
#9 Withコロナが暴く社会の底抜け
#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為
#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢
#12 Withコロナが予感させる不穏な未来
#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係
#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ
#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?
#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み
#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ
#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体
#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ
#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの
#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ
#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗
#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1
#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5
#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2
連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ
#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る
#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく
#3 子どもの教育をめぐる動き
#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”
#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと
#6 「学び」を通して主役になる
新着コンテンツ