
【張り子作家・アート大福さん】絵本のように可愛く不思議な世界。まったくの未経験から独学で作家活動をスタート。「私にもできる!」と思ってほしい
2024.02.20
子育て・教育
2022.01.5

この記事を書いた人
牧野 篤

東京大学大学院・教育学研究科 教授。1960年、愛知県生まれ。08年から現職。中国近代教育思想などの専門に加え、日本のまちづくりや過疎化問題にも取り組む。著書に「生きることとしての学び」「シニア世代の学びと社会」などがある。やる気スイッチグループ「志望校合格のための三日坊主ダイアリー 3days diary」の監修にも携わっている。
日本の学校は成功したのでしょうか? 大学という場にいて、ふと、そんなことを考えたくなるときがあります。
それはまた、社会的な格差が開いていることを、子どもたちや若者たちが自己責任として引き取ってしまおうとするような雰囲気が、この社会に広がっていることともかかわりがあるのかも知れません。
白熱教室で有名なマイケル・サンデルさんも、このような社会の風潮を憂いているひとりです。
サンデルさんは『実力も運のうち—能力主義は正義か?』(鬼澤忍訳、早川書房)で、サンデルさんが教鞭を執っているハーバード大学の学生たちが、恵まれた家庭環境に育ち、有名大学に進学することを支える様々な条件を持っていることを括弧に入れて、自分は人一倍がんばったからこの大学に進学している、自分は自分ひとりの力でこの大学への入学を勝ち取ったのだと本気で考えていること、しかも政府が大学進学を後押しするような政策をとっているのに、大学に進学できない人たちは、がんばろうとする意欲を持たないダメな人間だと、学歴を人間性の問題として扱っていることに警鐘を鳴らしています。
▶マイケル・サンデル、鬼澤忍訳『実力も運のうち—能力主義は正義か?』(早川書房)
しかも、アメリカでは、それが民主党の持つエリート意識とも結びついていて、社会をエスタブリッシュメントとその人々にバカにされる層に二分してしまい、バカにされていると感じている人たちがトランプ現象を巻き起こした、と指摘しています。
私のいる大学でも、私が触れあう学生たちがすべてそうだというわけではありませんが、確かに裕福な家庭の子どもたちが多い中で、彼らがある種の優越感を持っていて、その優越感は、自分のようになれない若者への人格的な優越感なのではないかと、彼らの言動の端々から感じることが多くなっているのも事実です。自分のようになれない同年代の若者たちをバカにしているのです。日本でも、安倍政権がすくい上げていたのが、こうしたバカにされる若者たちだったという指摘もあり得るのではないでしょうか。

連載第19回で紹介したブレイディみかこさんのいう「アンダークラス」の人々も、そうやって社会の主流から排除され、バカにされ、尊厳を奪われて、積極的に生きようとする気力を失い、社会保障にすがって日々をやり過ごそうとしている人々でした。
そしてその人々が生活する地域では、子どもたちは働くおとなの姿を見ることがなく、自分の人生のロールモデルを失って、またアンダークラスへと再生産されていってしまいます。これをブレイディさんは「国畜」という身も蓋もない言葉で表現していました。
そして、前回取り上げた「親ガチャ」ハズレた、という表現も、こういう若者たちが自分の置かれた境遇を自分なりに解釈して、自分を納得させ、その理由をも自分に引き取ろうとしてつくり出した言葉なのかも知れないという思いがつきまとうのです。すべては自己責任であるとして。そこでは、サンデルさんの著書の日本語版タイトルをもじっていえば、「運も実力のうち」といわれているように思えます。
連載第6回から9回にかけて、日本の学校に働く巨大な慣性力についてお話ししました。そして、18回・19回では子どもたちを襲う「諦め」について語ってきました。これらの議論をしてきて、日本の学校はそれでも成功したのだろうかと、改めて考えざるを得ません。
確かに過去、日本の学校教育が賞賛された時代がありました。
たとえば、戦後の高度経済成長を経て、安定成長に移り、さらにバブルの時代へと向かおうとするとき、日本の経済的強さの秘密を探ろうと、先進国で日本研究が盛んになされたときがありました。とくにアメリカでは、日本からの集中的な輸出に国内産業が打撃を受ける中、日本の強さを探る研究が花盛りだった時期があります。
その典型的なものにエズラ・ボーゲルさんの『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(広中和歌子・木本彰子訳、阪急コミュニケーションズ)があります。1979年の翻訳出版でした。
▶エズラ・ボーゲル、広中和歌子・木本彰子訳『ジャパン・アズ・ナンバーワン』(阪急コミュニケーションズ)
この本の中で、ボーゲルさんは、日本の経済力の秘密はたくさんあるが、中でも小中学校教育の優秀さがそれだと説いていました。
教師ひとりに児童・生徒が45人も、50人もいて、その子どもたちが、教室で荒れることなく、静かに授業を受けている。こんなことはアメリカでは考えられない。

こういう規律を遵守し、物事をきちんとこなし、かつ誰もが同じ高い学力水準を持った労働者として育成されること、こういうことが日本の製造業の強さの秘密なのだ。日本の企業が単に労働生産性に優れた組織体系をつくっているからだけではなく、むしろそのような体系に馴染み、黙々と規律正しく、ノルマをこなすことができる労働者が、学校で育成されているからこそ、日本の製造業は高い生産性を誇り、高品質で廉価なメイド・イン・ジャパンの製品を次々と世に送り出し、アメリカを凌駕するような経済成長を続けてきたのだ、というような趣旨が語られていました。
1979年といえば、私が大学に入学した年です。高度経済成長期に生まれ、日々豊かになるモノに囲まれつつも、大気汚染などの公害で小児喘息を患い、また受験地獄と呼ばれる選抜とそのための詰め込み教育を受け、さらにセンター入試の前身の共通一次試験の第一回受験者であった、つまり偏差値世代の走りだった私には、ボーゲルさんがおっしゃる日本の教育の優秀性は、子どもたちの苦しさを無視した、勝手な議論にしか思えませんでした。
しかし、ボーゲルさんはアジア研究の権威らしく、日本の成功体験が将来、日本の足枷にならないことを祈る、というような言葉を残しているのです。
私は大学の教員になってから、1995年にほぼ一年間、カナダに滞在する機会を得ます。そこでもカナダの小学校の教員たちから、日本の教育の優秀性を説かれ、日本がゆとり教育に舵を切っていたことに対して、一体なぜ日本はその優れた教育を捨てて、われわれが失敗した活動中心主義的な教育を採用するのか、と何度も問い詰められたことがあります。
1990年代になっても、日本の学校教育は優れていると思われていたのです。この時の経験は、拙著『多文化コミュニティの学校教育—カナダの小学校より』(学術図書出版社)にまとめられています。
▶牧野 篤『多文化コミュニティの学校教育—カナダの小学校より』(学術図書出版社)
しかし私には、自分の経験に照らしても、日本の学校教育が他国から賞賛されるようなものだったのか、しっくりしないものが残り続けていたのも確かなのです。
それは経済発展、とくに近代産業社会と呼ばれる、工業を中心とした、大量生産・大量消費の経済、つまり「量」の経済の社会において、人間を道具として考え、一人ひとり異なった個性を持った固有の存在ではなく、むしろ「量」つまり「人口」として扱い、労働力・購買力と見なしたときに成立する議論なのではないかと受け止めていたのです。

確かに、経済発展し、人々の物質生活の改善を進めること、そうすることで貧困を解決し、栄養や衛生そして医療を改善することで、人々の健康を増進し、さらに福祉も拡充して、社会を安定させること、そうして中間層を増やし、購買力を強化して、市場を発展させることができ、経済発展をさらに推し進める、こういう循環をつくることが可能となります。そしてそこでは、人々は一人ひとり異なった存在ではなく、「人口」として扱われます。
これは17世紀末の重商主義の時代以降の市場社会の基本的な考え方です。社会主義や共産主義の社会においても、人々は個別具体的な存在ではなく、むしろ政策の対象としての道具つまり「人口」という「量」でしかありません。
このような考え方では、学校は集団主義的に構成され、子どもたちは一人ひとり異なった存在だとみなされるよりも、皆、均質だからこそ相互に量的に測定可能で、序列化可能な、つまり代替可能な普遍的な存在として扱われます。
ですから、学校では部分最適、つまり最大多数の最大幸福とでもいえばよいような、みんなが同じような水準になっていることが理想とされ、そのためにがんばることが奨励されることとなっていました。
ここに違和感があったのです。
それは人口が増加し続け、市場が拡大し続けるという「量」の経済を基本とした社会の仕組みの一部でしかありません。
この社会の基本は、均質と平等です。つまり、誰もが同じ人々として他者と同じであり、だからこそ平等に扱われなければならず、平等に扱われることで、他者と自由に競争して、序列化が可能となる、しかもその序列の中では誰もが入れ換え可能であるという観念が一般化します。

それが可能となるのは、社会的な分配が増えること、つまり人口が増えて分配の割合が減っても、経済が発展し続けて、もとのパイが大きくなり続けることで、分配の量が増え続けること、それが保障されているからでした。それは、自由と平等のトレードオフを止揚するパイの拡大を宿命づけられている社会なのです。
日本の社会は、自由と平等のトレードオフを調和させるような博愛という観念を十分に育てることがないままに、キャッチアップ型の経済を発展させ、それが愛国心に結びつけられて他国との競争を煽る、欧米先進国に追いつき追い越せの競争を勝ち抜くことを宿命づけられてきたのだといってよいでしょう。その条件は何かといえば、経済の量的な拡大と一人ひとりへの分配の増加です。
学校もその社会のシステムを構成する一つの制度です。ですから、学校でもみんなが同じであること、平等に扱われることと競争することは、矛盾することなく、同居していたのだといえます。むしろ同じで平等だからこそ競争が成立するのです。
このような社会と学校の在り方は、明治の初めからそのようにつくられたといってもよいのかもしれません。
たとえば、中村正直が訳出した『西国立志編』(サミュエル・スマイルズ、中村正直訳、講談社学術文庫)は、明治3年(1870年)の刊行で、有名な「天は自ら助くるものを助く」という言葉とともに、ヨーロッパの立志伝中の人々300余名を取り上げたある意味でのケースブックですが、発行部数100万部を下らないといわれたベストセラーでした。
▶サミュエル・スマイルズ、中村正直訳『西国立志編』(講談社学術文庫)
原著のタイトルがSelf Helpつまり「自助」であったものを、「西国立志編」と訳した中村の才覚には脱帽ですが、それはまたその時代の雰囲気を体現していたのではないでしょうか。自助と立志が重なるのです。自助の精神とは、他人の力に頼らないことであり、それが人たるものの才知の根拠でもあると述べ、そういう人が多ければ多いほど、その国も気力が充実し、国力も高まる、そのためには刻苦勉励が必要だと説いています。
このことはまた福沢諭吉の『学問のすゝめ』(岩波文庫)ともかかわっています。
福沢も新しい日本社会をつくるために、社会の構成員としての個人の自立を説き、「一身独立して一国独立す」というように国家の独立と発展を担う責任を自覚することや社会を自らの責任として受け止めることを説き、自助を超えて、人々一人ひとりの社会的責任にまで言及しています。
そしてその背景にある思想が、「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」、つまり人は生まれもって平等であるという理念です。

そしてこういうのです。「独立自尊」。そのためにこそ、「学べ」というのです。
本来社会は、そういう開かれたものとして、自助努力を実現させることができる場として受け止められていたといってもよいのではないでしょうか。ただ、その裏返しとしては、努力しないものには社会は機会を提供しない。つまり、「天は自ら助くる者を助く」ということなのです。
そして、学校はその場としても考えられていたのではないでしょうか。『西国立志編』や『学問のすゝめ』を取り上げるまでもなく、明治5年(1872年)に出された「学制」の前文に当たる「被仰出書(おおせいだされしょ)」には、次のように明記されています。
「學問ハ身ヲ立ルノ財本共云ヘキ者ニシテ人タルモノ誰カ學ハスシテ可ナランヤ夫ノ道路ニ迷ヒ飢餓ニ陷リ家ヲ破リ身ヲ喪ノ徒ノ如キハ畢竟不學ヨリシテカヽル過チヲ生スルナリ」。【(現代語訳)学問は立身のための資本ともいうべきものであって、人たるものは、誰が学ばないですまされようか。あの、路頭に迷い、飢餓に陥り、家を破産させ、わが身を滅ぼすような人たちは、結局は学ばなかったがために、このような過ちを生んだのだ。】
そして、その立身出世の財本である学問を民衆にさせるために学校を設ける、というのです。
すでにここに自助努力の必要と結果の自己責任が書き込まれています。
しかし連載第7回でも指摘したように、実際には学校はそのようには機能してきませんでした。
立身出世・階層上昇を個人の努力によって可能としたのは、学校によって子どもたちが同じように扱われ、もともと個人としては平等であった子どもたちが、学校において努力すること、つまり「天」すなわち生まれによって「人の上」でも「人の下」でもない子どもたちが、刻苦勉励して、「自ら助くる」ことを通して、「独立自尊」を勝ち取ろうと努めることで、それを勝ち取ることができたのは、社会が経済的に発展し、パイの拡大がなされていたからであって、学校そのものが拡大再生産の経済発展によってのみ、国民の求心力を高めることができる制度だったのです。ここに学校の背理があります。
学校とはもともとは、個人の努力では変えることのできない生まれや家庭そして様々な環境の格差があるからこそ、その境遇から子どもたちを引き離して、均質で画一的な時空間において、努力にもとづく平等の競争を組織することで、子どもたちをこの社会の成員として育成し、彼らが競争し続けることで、社会の発展とくに経済発展を促し、その結果を人々に還元することで、物質的な豊かさを保障する仕組みだとされた制度でした。それはまた、他者と平等になり続けることを求める際限のない競争でもあったと言えるかもしれません。
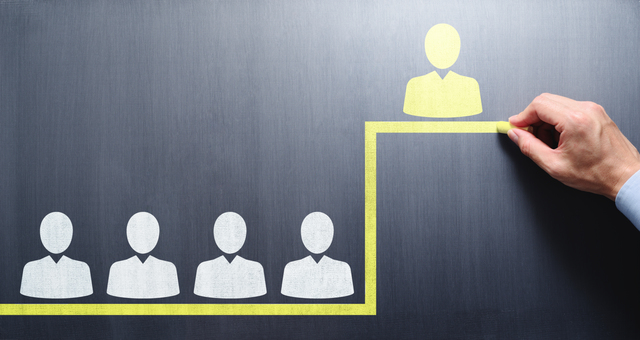
しかし、その学校は実は、失敗し続けることを宿命づけられていた。そういうこともできるのではないでしょうか。
学校は人々の、とくに子どもたちの将来を、学歴という形で規定すると、世間的には受け止められています。
学校は、工業社会という拡大再生産の市場社会において、核家族と会社とを、子どもの選抜を通して結びつけ、家計の世代的な向上を促す仕組みだとみなされてきました。
そして、学校で努力してよい成績を取りさえすれば、自分の生活を向上させることができるというのがこの社会の「信憑」でした。しかし、すでに明らかになっているように、それは幻想だったのかも知れません。
学校が選抜してきたのは、端的には、サンデルさんがおっしゃる家庭の経済力ですし、それにかかわる様々な文化的・心理的な要因です。

そして、学校が経済発展に有効に機能してきたのは、経済そのものが拡大する「量」の経済であったからです。
このことは、もしかしたら、学校がなくても経済は拡大基調を保って、発展してきたのではないかとの疑問を抱かせます。
学校がやってきたのは、この拡大基調の発展する経済を、人材育成をとおして、つまり勤勉な労働力と旺盛な購買力の育成を通して、後押しして、発展速度を速めただけのことだったのかも知れません。
それはいいかえれば、経済が拡大しなくなれば、または経済の在り方が「量」の経済から「質」の経済に切り替わり、価値観が多様化して、個別最適が目指されるような社会になれば、学校は機能不全に陥る宿命を負ったものだったということではないでしょうか。
学校は、社会経済をつくりだすものではなくて、その必要から生まれた制度でしかなく、社会経済の在り方が異なれば、また変化せざるを得ないものなのではないでしょうか。
そして、この「量」の経済の時代はすでに終わり、新しい時代が到来しているのではないでしょうか。
私たちのこの社会は、これまでのような拡大する「量」の経済の時代ではなくなって、すでに30年にもなろうとしています。
それは、人口の構造を見ても明らかなことです。日本が高齢化する社会に入ってすでに半世紀が過ぎ、少子化と高齢化が同時進行して高齢社会になったのが1994年、そして人口減少が明らかになったのが2006年です。人口だけを見ても、拡大する「量」の経済の維持はすでに不可能になっています。

だからなのではないでしょうか。人口減少に対して経済界から強い危機感が示され、少子化対策に様々な手が打たれたのは。しかし、少子化を止めることはできず、むしろ今日の経済状況は、それに拍車をかけることとなってしまっています。
それは、この国がいまだに拡大する「量」の経済の観念に縛られたままになっていて、その観念の下で政策が策定され、実施されているからなのではないでしょうか。
そして学校もまた然りなのではないでしょうか。「親ガチャ」ハズレたという若者たちの存在、コロナ禍で明らかとなった若い女性たちの非正規雇用の急激な拡大と失業、そしてそれにともなう自殺者の急増などがそれを改めて物語っているとはいえないでしょうか。
このような学校の状況に対して、コロナ禍は子どもたちに異なる風景を見せることになったとはいえないでしょうか。
オンラインで授業を受けることができ、さらに様々な学びをとめない取り組みがなされることで、学びは学校だけではないことに、多くの子どもたちが気づき始めています。
そして、学校という場で行われる学びが、いかに窮屈で、また退屈なことなのか、ということも感じ始めているのではないでしょうか。
スタディサプリに代表されるオンラインの授業で、学ぶことの愉しさと探究することの面白さを知った子どもたちは少なくありません。

また、オンラインで授業を受けつつ、地域コミュニティで多くのおとなたちと交わることの楽しさを感じた子どもたちもたくさんいます。
もちろん、学校という場でなければ得られないものもたくさんあります。友だちと遊ぶことや部活動それに生徒会などの活動は、その一例です。そして子どもたちもこのことについては、誰もが学校の魅力だとしてあげています。
しかし、授業を受けることについては、オンラインに魅力を感じている子どもも増えてきているのではないでしょうか。しかもその子たちは、皆同じに扱われて、結果的に比べられて、序列化されるよりは、皆一人ひとり異なった存在だと認められ、自分で学びを深め、学んだことを互いに教えあって、異なっているからこそ一緒に学べるという環境をつくりだそうとしているように見えます。
彼らは、学校が持つ時空間とは異なる時間と空間を、それこそオンラインのネットワークの中につくり出して、新しい学びを生み出そうとしているかのようです。
コロナ禍は、学校の失敗が「量」の経済の失敗によって宿命づけられていることをようやく私たちに気づかせてくれたのではないでしょうか。
しかし、緊急事態宣言が解除となった途端に、学校が元に戻っていってしまうかのような事態を目の当たりにしなければならなくなっています。学校にはいまだに巨大な慣性力が働いているのでしょうか。
そうだとしたら、学校を変えることはとても時間のかかる至難の業だといわざるを得ないのかも知れません。
それよりも、学校とは異なる「学び」の場をつくって、そちらを大きくしていくことで、結果的にこの社会における「学び」の仕組みを変えること、そういうことが必要になってくるのではないでしょうか。

Withコロナの時代、私たちには新しい「学び」の仕組みを社会に生みだし、実装することが求められているのかも知れません。
\ 人生100年時代の社会のグランドデザインを描く/
\ 最新情報が届きます! /
牧野先生の記事を、もっと読む
連載:子どもの未来のコンパス
#1 Withコロナがもたらす新しい自由
#2 東日本大震災から学ぶwithコロナの中の自由
#3 Withコロナで迫り出すこの社会の基盤
#4 Withコロナがあぶりだす「みんな」の「気配」
#5 Withコロナが呼び戻す学校動揺の記憶
#6 Withコロナが再び示す「社会の未来」としての学校
#7 Withコロナが暴く学校の慣性力
#8 Withコロナが問う慣性力の構造
#9 Withコロナが暴く社会の底抜け
#10 Withコロナが気づかせる「平成」の不作為
#11 Withコロナが気づかせる生活の激変と氷河期の悪夢
#12 Withコロナが予感させる不穏な未来
#13 Withコロナで気づかされる「ことば」と人の関係
#14 Withコロナで改めて気づく「ことば」と「からだ」の大切さ
#15 Withコロナが問いかける対面授業って何?
#16 Withコロナが仕向ける新しい取り組み
#17 Withコロナが問いかける人をおもんぱかる力の大切さ
#18 Withコロナで垣間見える「お客様」扱いの正体
#19 Withコロナで考えさせられる「諦め」の怖さ
#20 Withコロナ下でのオリパラ開催が突きつけるもの
#21 Withコロナで露呈した「自己」の重みの耐えがたさ
#22 Withコロナであからさまとなった学校の失敗
#23 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1
#24 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・1.5
#25 Withコロナの下で見えてきたかすかな光・2
連載:学びを通してだれもが主役になる社会へ
#1 あらゆる人が社会をつくる担い手となり得る
#2 子どもたちは“将来のおとな”から“現在の主役”に変わっていく
#3 子どもの教育をめぐる動き
#4 子どもたちに行政的な措置をとるほど、社会の底に空いてしまう“穴”
#5 子どもたちを見失わないために、社会が「せねばならない」二つのこと
#6 「学び」を通して主役になる
新着コンテンツ